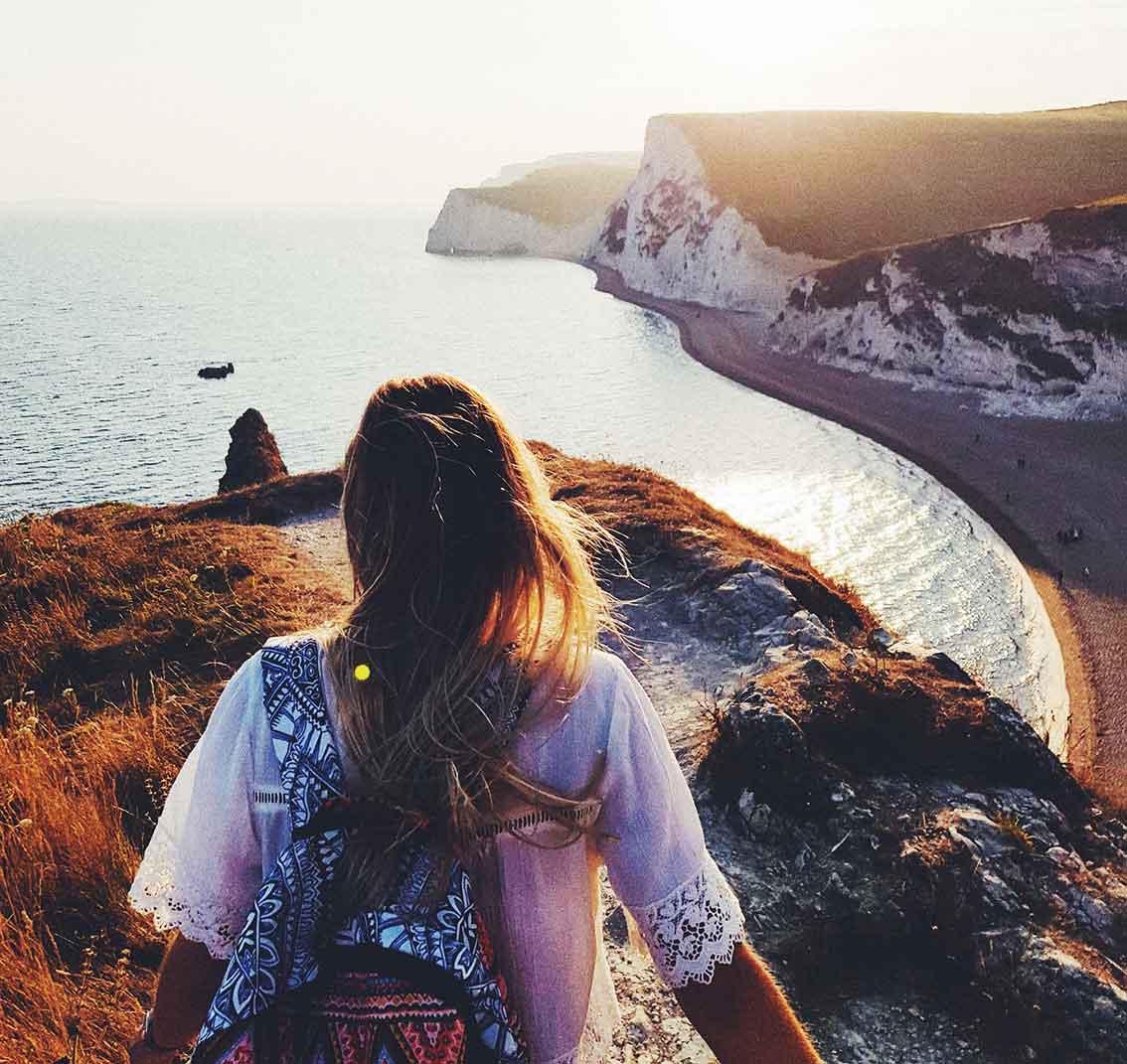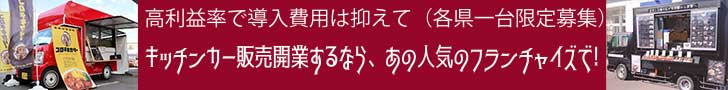これからキッチンカー開業を検討している場合、最初に立ち塞がるのが「メニュー」と「開業資金」でしょう。
今回の記事では既存店舗のキッチンカー導入ではなく、新規開業(起業)に絞ってメニューの決め方と資金調達を解説していきます。参考にしてみてください。
メニューの決め方

どうして最初にメニューなのかといえば、メニューが決まらないとキッチンカーのタイプすら決まらないからです 笑。
一番いいのは自信のあるメニューです。これから開業ですから運営した経験はほとんどないはずですが、自信を持って提供できるメニューがあるのならそこで勝負するべきでしょう。
まわりに競合するキッチンカーがあるかどうかって気にする人がいますが、全く気にしなくて良いです。これは後で触れますが、競合店を気にして自信のあるメニューを避けるのは間違いです。思いとどまってくださいね。
得意なメニューがない場合
調理経験も飲食店の厨房で働いたこともない場合でも大丈夫です。ほとんどのキッチンカーは最初はそういった立場から開業しています。
それではまっさらな状態から絞っていきましょう。
人気メニュー10選(軽食は除く)
調理経験が自宅以外でない場合、人気の(売れる)メニューをリサーチするところから始まりますよね。
キッチンカー運営現場から「一年通して」「よく売れているメニュー」をピックアップしてみます。
あちこちで人気メニュー10選を見かけますが、地域性や時代(現在2023年)もありますし、主観も混じっているので若干意見は割れますが、僕の選んだオススメ10選は以下の通りです。
- 焼き鳥
- カレー
- 丼もの・弁当
- から揚げ
- たこ焼き
- クレープ
- コッペパン
- ピザ
- 焼きそば
- ハンバーガー
なお、軽食はお勧めしません。極力省きましたが、「クレープ」や「たこ焼き」などは一年通して売れるので入れました。
軽食を含まない理由について、詳しくはこちらを参考にしてみてください。

どれも売れる保証はない

気になるメニューはいくつかあったでしょうか?できるできないは置いといて、お客さん目線だとどれが気になりますか?
自信を持って提供できる商品がない場合は、お客さん目線になって欲しい商品の方が心から薦められるのではないでしょうか。
販売データもお客様の反応も、今回は何もないところからなので、まずは軸になるメニューを決めることが先決です。
どれを選んでも売れる保証はありません。ここで立ち止まってしまうか腹を括るか。実際にやっている人とそうでない人の決定的な違いでしょう。
今回は好きか嫌いかで決めるような書き方になっていますが、本来はメニューの継続や廃止についてはきちんとした決まり事があります。
商売の基本として、いくら手間暇かけて思い入れがあっても売れない場合はメニューから外すべきなんです。逆に半製品で調理もほとどんどしない商品でも、売れているなら外しちゃいけません。
食材にこだわって手間ひまかけて愛情があっても売れない商品は、自宅で趣味で作るメニューだということです。これが商売として正しい考え方です。実際に事業が始まったら、この基準で商品を正しく判断してくださいね。

競合店は気にしないこと(重要)
お住まいの街にカレーの有名キッチンカーが活動していたとして、やろうと決めたカレーを控えるのは大きな間違いです。競合店をリサーチするのを推奨する人がいますが、そもそも何にも意味がありません。
そもそもキッチンカーは移動販売だということ。
それ以前に飲食店を開業するのに、街に人気のカレー屋さんやラーメン屋さんがない街なんてありません。もっといえば、後から人気店が生まれたら引っ越しますか?っていうくらい無意味なリサーチです。
そんなことよりも自分が提供するカレーに集中して個性や質を上げる方にエネルギーを使いましょう。人気のカレー店が二つや三つある方が、カレーフェスティバルが出来るって考えるくらいポジティブな思考を持ちましょう。(実際当社でカレーのキッチンカーやっているのですが、カレーフェスティバルやったところカレー嫌いな人は少ないようで盛況でしたよ 笑)
軸が決まれば設備と食材でメニューは広がります
から揚げ店をするとしたらどんな設備が必要でしょう。
目玉商品がから揚げですからフライヤー(揚げものの揚げ機)は設置しますね。ということは、かき揚げだってポテトフライだって出来るわけです。チーズでも串揚げでも揚げると何でもメニュー化しますので、サイドメニュー開発は困らないでしょうね。
ではクレープ屋さんならどうでしょう。
クレープ専用の焼き機ですからフライヤーのようにはいきません。しかしコンロも揃えるはずです。生地を作るのに牛乳を温める必要があります。
コンロだけでメニューの幅も広がりますが、食材の方でドリンクも扱う可能性大ですしチョコソースや生クリーム、フルーツも使うことでしょう。
こうして軸になる商品を仮にでも決めてしまえば、お店のスタイルがぼんやりしていたところから具体的に見えてくるはずです。
メニュー決めは最初はここまでにしておきましょう。商品化に向けて盛り付けやパッケージ、付け合わせやネーミングなど決めていくことはたくさんありますが、軸になる商品が決まれば資金調達の準備に取り掛かりましょう。
金融機関とのやりとりをしている間に、メニューにまつわる事は一つ一つ進めていけば良いと思います。
キッチンカー開業の資金調達

続いては開業をためらうもう一つの大きなハードル「開業資金」について。
事業を始めていると融資も補助金も「営業実績」があるので比較的簡単なのですが、創業となると金融機関も事業計画の信憑性が実績に基づいていないのでシビアになるのは必然です。
ポイントは創業計画。具体的に説得力のある計画の立て方をお伝えしていきます。
創業計画の肝となる項目
融資の申し込みは「事業計画書(創業計画書)」が肝心要です。事業の展望・将来性を担当者に理解していただき、その上で自分が取り組む内容を文章と数値で理解してもらう書類です。
事業資金の肝になるのはメニューと車両。これさえ決まれば計画も具体的に作成できますので進めていきましょう。
※事業計画書についてはこちらもどうぞ

創業計画書作成のポイント
✔創業計画書はいくつかのテーマを設けて作成します。下記の4項目に分けて作成するといいでしょう。
それぞれ記載する内容を自分に当てはめて、まずは書いてみましょう。
| 創業の経緯 |
|
| 事業の現状・将来性 |
|
| 取組み・個性 |
|
| 資金計画 |
|
✔ 書けるところまで書いてみましょう。詰まってしまいそうなところを次で説明していきます。
具体的な説明で詰まった場合
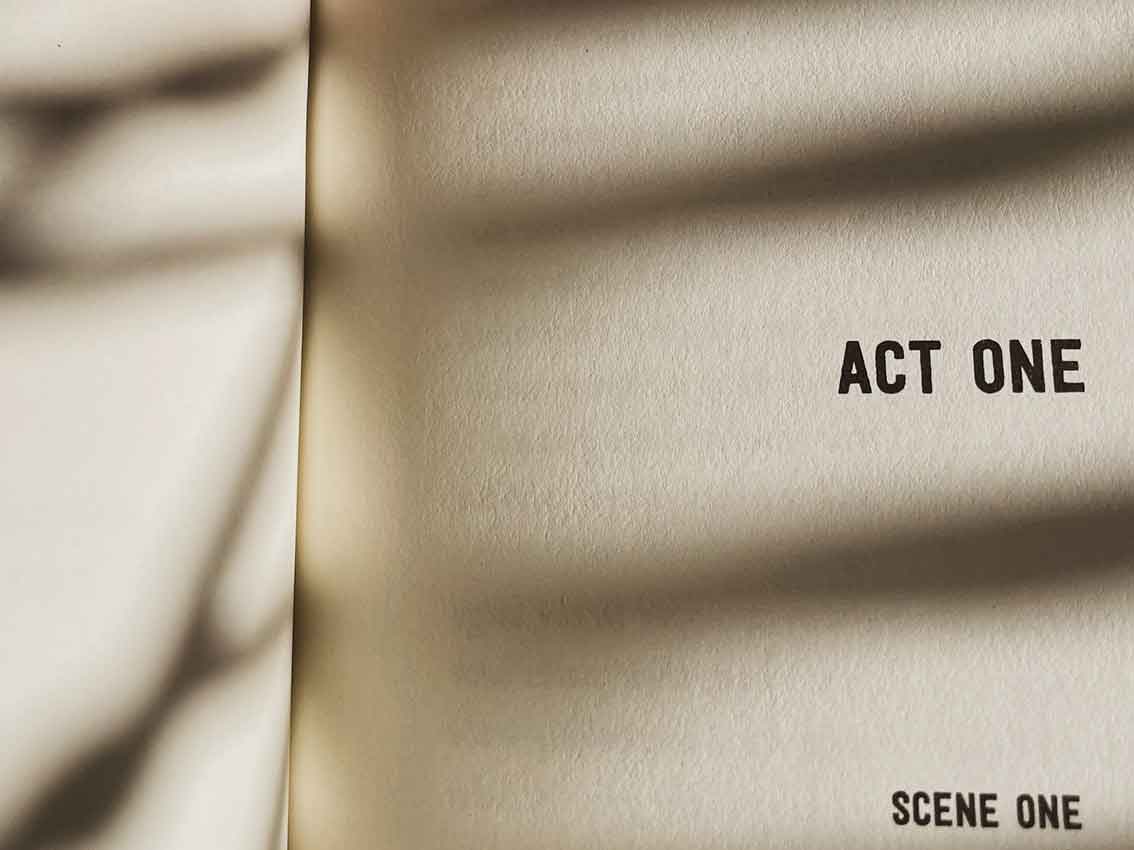
✔ それでは創業の経緯からです。自分の履歴については問題ないでしょう。資格があれば記入をお忘れなく。
「創業のきっかけ」と「事業で実現したいこと」は内容的に被ることもあるので、一つとみなして書き進めるのもありです。今よりも収入を増やしたいというのは当たり前の話ですから、遠慮せずに書き加えて構いません。出来れば「自分のスキルを活かして」「目標をもって達成感や経験を積みたい」というワードも散りばめるとよりいいものになります。
続いてはキッチンカー業界の現状と将来性になります。例文を挙げると
コロナ禍により全国的に外出自粛の風潮となり、外食離れが進むなか注目を浴びているキッチンカー業界です。
飲食店経営者が事業形態を変えて参入や、創業での参入など毎年新規参入が相次いでいます。現在(2023年2月執筆)の市場は、まだまだ需要の方が多いということと、キッチンカーをトリガーにして事業展開を発展させている事業者も多いです。
業界は未成熟ですが、いずれ供給も追いつくのでそれまでに基盤を作り事業として形作っていきたいと考えています。
といったような感じです。現在の状況はこちらの記事で詳しく触れています。

事業の発展形態の一つです。こちらの記事もどうぞ

✔続いては「取り組みと個性」です。取り扱うメニューの提供とキッチンカーの車両購入に向けて、どういった取引先が必要でどの程度決まっているのか。販売促進の物品の手配や消費者への告知方法まで、進捗状況を書き出しましょう。
合わせて自分のキッチンカーの個性や強みをスパイスとして加えて下さい。必ず自分のスキル・経験でなくても構いません。親しい友人や知人からサポートを頂いて身につけた、または身につけるスキルでも構わないでしょう。
決して奇抜なアイデアが必要なわけではありません。実際は運営していく中で工夫・改善をしていくのですが、ここでは今現在自分が持っているすべてのネタを書き出しましょう。
もう一つ大切なポイントは出店見込みです。つまりは毎月の稼働がどれほど見込めるかということです。出店先を増やす記事は下記を参考にしてみて下さい。


✔続いて資金計画ですね。初期費用から行くと
- 車両購入費
- 車両に必要な広告の備品(タペストリーなど)
- メニュー開発材料費
- 厨房内設備(電子レンジや冷蔵庫など什器備品)
- 厨房で使用する備品(フライパンからゴミ箱まで)
- 最初の契約で必要な資金(車保険や駐車場の敷金など)
- 開業時の原材料在庫(調味料なども含めて)
上記のモノたちの金額をわかる範囲で書き出しましょう。他にも思い当たる費用は付け足して書き出して下さいね。
最初に必要な資金が出たら、自己資金を引いて不足の金額を出しましょう。この金額が融資申し込み金額になります。少し余裕を持って始めたいので初期費用は思いつく費用はどんどん記入しましょう。
✔次に毎月の運転資金です。ざっと以下の通り。
- 仕入(予想売上×原価率)
- 駐車料(仕込み場所が他にあれば家賃)
- 光熱費(電気・水道・ガス・灯油)
- ガソリン代(予想出店数をもとに計算)
- 消耗品費(使い切りの物:ティッシュやビニール手袋など)
- 車両保険料
- 家賃(出店先によります)
代表的なランニングコストはこんな感じです。原価率はもちろんそれぞれ違いますから、しっかり計算して把握していて下さい。
出店料は概ね3,000円くらいです。かからないところの方が多いです。なので平均1,500円に出店数をかけたくらいが妥当でしょう。
毎月必要な費用がわかれば、売上の見込みからいくら利益の金額が出ます。生活費が入っていないのでハードルはかなり低いはずですが、この利益こそが収入(生活費含む)ですからたくさん残る予定であって欲しいです。
忘れてはいけないのが、利益から借入の返済金も払っていきますし決算申告後には税金の支払いもあります。こうした資金も賄えない計画では融資は出ませんので忘れずに確認して下さい。
※借入額がわかればこちらから毎月の返済金を算出できます
✔最後に創業後3年間の資金の流れをエクセルなどで表にして作成しましょう。
年月の欄に毎月の予想売上を書いて、その下に仕入れと毎月の費用、さらに下に返済金を記入します。売上から順に引いて残った金額が利益です。これを3年分作成しましょう。
年間どのくらい利益が出そうですか?大きな売上が見込める夏から秋と冬から春先までは売上も変動してないとおかしいです。さらに2年目3年目はこの先の事業展開に合わせて数字を書き込めばなおさらいい計画書になります。
叩き台が出来上がったら

まずは自分で書いてみることがとても大切です。書き込んでいるうちに、ぼんやり思い描いていたものが具体的に見えてくるはずです。
書けば書くほどやらなければいけないことが出てきます。こうして気づきがあることは大切なんです。気がついた時にメモ帳か付箋にでも書いて忘れないようにしましょう。
ある程度の叩き台が自分の力で出来たら、申し込みに行く前に日本政策金融公庫の「創業サポートデスク」というサービス(もちろん無料)を利用してみて下さい。何もわからない融資希望者にも対応していますから、ここまで叩き台ができていて「この先どう進めたらいいか」尋ねればかなり印象が良いはずです。(申し込むだけなんですが 笑)
※日本政策金融公庫:創業サポートデスク(動画解説あり)
※日本政策金融公庫:全国の店舗一覧
ここからが最初の一歩です
こちら 今回はあくまでも創業者向けの記事ですが、決めていくことと書類を作成する流れをお伝えしました。実際に取り掛かってみるとそんなに大変なことではないのがわかると思います。 何も取りかからないでいると、いつまでも難しそうに感じるだけです。ここまで読んで頂いていたら、ぜひ書類の自分の履歴から作成してみて下さい。やっていくうちにいろんな気づきがあって夢中になりますよ。 春先からの開業に向けて準備している人は多いです。キッチンカーの季節が始まると経験でどんどん先を行かれますので、今始められることからやってみましょうね。

あまりに最近の流れなので定かではありませんが、ちょっと気になっているので余談で紹介します。
大手スーパー(百貨店・ショッピングセンターも含みます)より、この春から系列店舗への出店を打診されたのですが、巡回のようなスケジュールで提案された通りに出店すると、ほとんどそこにかかりっきりになります。こちら北海道なので道内くまなくだと回りきれないほどです。もちろん週末はイベントも入ってきますから、平日のスケジュールでお願いしました。
同じような話を違うスーパーから打診されたキッチンカー仲間が何人かいます。あれれと。スーパーの戦略で囲い込みの流れなのかなと感じています。今度デベロッパーさんに会う機会があれば確認してみようと思いますが、続報がありましたらご紹介します。
キッチンカーで創業する場合はスーパーから営業をかけると良いかもしれませんよ。話がまとまれば、あっという間に出店カレンダー埋まりますからね。